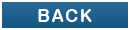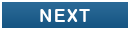|

ホーム >> 【個人のお客様への調査内容】 紛争事例
※「千葉県宅地建物取引業協会 研修会テキスト」 から抜粋したものです。
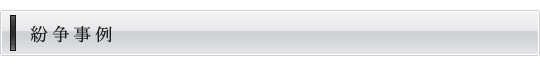 |
| |
 広告に記載された土地面積が実際と異なっていた 広告に記載された土地面積が実際と異なっていた |
売主業者の作成した広告に記載された土地面積が実際と異なっていたため、買主が融資を受けられなくなったとして、手付金の返還を命じられたケース
紛争内容
- 買主Aは、売主業者Bから土地・建物を3,850万円で購入する売買契約を締結し、手付金を支払った。
- 当該物件の面積は、実際には、土地面積が99.17m2、建物の廷床面積が67.50m2であるが、売主業者Bが作成した物件チラシには、土地面積が115.67m2、建物の延床面積が99m2と記載されており、実際と異なっていた。土地面積の差異は、私道の持ち分相当の面積であった。
- 買主Aは、契約締結の交渉の際、売主業者Bに対Lて、手持資金は1,500万円であり、勤務先から500万円の財形融資を受け、不足する1,850万円については住宅ローンを利用したい旨を告げていた。
- ところが、その後、財形融資について、中古の一戸建住宅の場合当該地の面積が100m2以上であることが融資条件であることから、同融資は受けられないことがわかった。また、その財形融資で予定した500万円を補充するため住宅ローンを2,350万円に増額することも不可能であることが判明した。
- そこで、買主Aは、売買契約は錯誤により無効であると主張して、手付金の返還を売主業者Bに求めた。
【買主Aの言い分】
売買契約の締結にあたり、財形融資が受けられることを前提としていたのに、これを断られたのは重大な見込み違いであり、当該物件の売買契約は錯誤により無効である。
売主業者Bには、私の代金の支払計画のことを十分に知らせてあったので資金計画について十分確認すべきであった。
【売主業者Bの言い分】
買主Aは、資金の余裕のない状態で財形融資を頼りに物件を購入するのだから融資の可能性または、不能の場合の対策等について配慮して契約を締結すべきであつた。ところが、Aはこれを利用可能と即断したのだから、Aに「重大な過失」があり、民法第95条但書により、自ら無効を主張できない。
【本事案の問題点】
- 売主業者Bが作成したチラシに記載された土地面積であれば、財形融資の対象となり得るのに、実際の面積では、融資要件を欠くことについてBは、十分配慮すべきであった。
- 売主業者Bは、契約締結前に買主Aの資金計画を告げられていたのであるから、住宅ローンの利用限度額について調査・説明をすべきであった。
- 買主Aのローンが成立しないときの措置について契約書に明記すべきであった。
【本事案の結末】
当事者双方の融資に関する認識内容から考えると、当該物件には財形融資がつくこと当然の前提としたところであるから、財形融資が受けられなかったことは買主Aにとつて要素の錯誤であり、売買は無効である。
民法上、要素の錯誤であっても、重大な過失により錯誤に陥ったときは自ら無効を主張できない。
Aが財形融資を利用可能なものと即断してあわただしく契約締結したことは軽率であった。
しかし、Bは業者であり、財形融資や住宅ローンのことについては、通常の人より精通していること、また、土地面積についてチラシと実際とで違っていたことが、本事案の原因となっていること、また、財形融資がAにとって重要であることを知っていながらその点の説明ないし助言などに欠けていたこと等を総合判断すると、Aに重大な過失は認められない。したがって、売買契約は無効であるとして、Bは、Aに対して手付金の返還を命じられた。
本事案に学ぶ
- 業者は、各種の融資制度について日頃から自己研鑚しておく
買主Aが財形融資を受けられなかったのは、融資条件の一つとして、土地面積100m2以上が必要であったにもかかわらず、売主業者Bは、そのことについて知らなかったためである。
Bが土地面積が100m2未満では融資が受けられないことを知っていれば紛争にならなかったと言える。したがって、業者としては日頃から各種の融資制度について自己研鑚しておくことが不可欠である。
- 資金を借入で調達する場合、ローン条項を契約書に明記する
建設省計画局不動産業室長通達により、ロ−ンによる場合は、少なくともその内容を重要事項説明書、契約書に明記することとされている。
したがって、業者は、買主が住宅ローン等を利用する場合、ローン条項を契約書に明記するよう留意する。
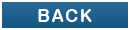 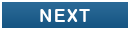 |
|
|
|
COPYRIGHT(C)2008 宅地開発設計 有限会社アットプレイン ALL RIGHTS RESERVED.
|
|

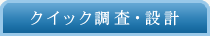
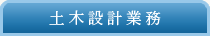
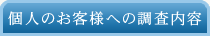
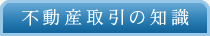
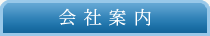

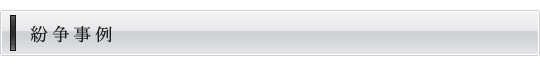
 広告に記載された土地面積が実際と異なっていた
広告に記載された土地面積が実際と異なっていた